 | |
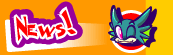 | |
 | |
 | |
| ●著者インタビュー ●イベントレポート ●リーダーズサーカス ●エッセイ ●TRPGリプレイ | |
 | |
|
| ←エッセイ目次 |
| 日々つれづれ 09年05月 テーマ 「 ミステリ 」 |
| 【05月22日 秋田みやび】 |
秋田はミステリー大好きです。 推理小説は一時期かなり片っ端から読んでいました。 どんでん返し系の推理小説などを読んで、途中で仕掛けがわかるとにやりと気持ち悪く笑い、その顛末が予想通りだと「勝った!」などと思ってしまいます。その瞬間は実に清々しい。 まあ、もちろん敗北することも多々あるわけですが。 さて、そんな秋田に、解けない謎があります。 それはおおよそ7年前の夏のことでした。 いそいそと雪○だいふくを買ってきて食べようとしたところ、二つ目のだいふくが、薄緑のフォークから刺されるのを嫌がるように、こんころりんと床に転げ落ちたのです。 大ショックでした。 「三秒ルールだから大丈夫」と無意味なことを呟きながら、拾い上げようとしたところ……。 その落ちたはずの雪○だいふくは、忽然と、人知れず姿を消したのです。 それはもう、慌てました。 丸いから転がるにしても、限度はある。そして季節は、やや涼しかった覚えもありますが夏です。融けたら大惨事です。黒くてちまっこい大群が我が家を来襲してしまう可能性もあります。 これは何としても捜索しなければ! のほほんおやつタイムが、一転して失踪だいふくの捜索現場と化しました。 片っ端から入り込みやすそうな隙間を覗き込み、家具を動かし、当然ハムスターやうさぎたちへと心当たりを聞き込みすることも忘れません。 ――かなり詳細に、マルサも真っ青の家宅捜索をしましたが、遺留品は何一つ見つかりませんでした。 一体、だいふくはどこに消えたのでしょう。 わかっているのは、その夏は黒いちまっこい大群の来襲を受けることもなく、その痕跡は引っ越した後でも見つけることはできなかったということです。 今でも、ふと……雪○だいふくを食べると思い出します。 彼は、一体どこにいったのだろう、と。 その他にも、飼っていたハムスターの密室脱出トリックが解けなかったり(そのお陰で鞄に入り込まれ。会社まで連れて行ってしまったことがある)、ことあるごとに文鳥に腕を齧られる傷害事件を未然に防げなかったり、猫の秘技バックスペースタッチによる原稿文章消失に愕然としたりと、様々な謎に日々遭遇します。 いやー、世界はミステリーで満ちていますね。 |
| 【05月07日 秋口ぎぐる】 |
メイドさんがマッサージしてくれる店に行った。 そこで偉大なる人物と出会った。 順を追って書こう。 おれは友人の岩崎さんと一緒に日本橋の街を歩いていた。とある交差点でマッサージ店の立て看板を見かけた。そこにはメイドさんや店内の写真、料金表などと共に、「料金30パーセントオフ」という非常にお得と思われる割引券が貼られていた。 もちろんおれと岩崎さんは食いついた。興味津々だった。ぜひ行ってみよう、という話になった。 割引券に描かれた地図を頼りに、おれたちは大通りから外れ、脇道に入った。すぐにそれらしい看板が見えてきた。 おれたちは店の前に立った。店の正面はガラス張りになっており、中の様子を見ることができた。喫茶店のような造りだ。入り口の近くにレジカウンターがあり、向かって右側にテーブルと椅子が並んでいる。それぞれの席では何人かの客が飲み物を前にし、漫画なんぞを読んでいた。メイドさんの姿は見えない。 猛烈に入りにくい雰囲気だった。地方都市で明らかに常連客しか入っていなさそうな場末のスナックを前にした感じ、と言えばわかっていただけるだろうか。 おれも岩崎さんも根性と勇気と意気地がない点にかけては筋金入りなのだ。 これは無理だ、絶対に入れない、帰ろう……と思っていたところ、店内から1人の客が出てきた。店の前に置かれたベンチに座り、ポケットからタバコの箱を出した。よく見るとベンチの前には灰皿が置かれている。店内は禁煙なので、外に出て一服するつもりらしい。 その客はおれたちよりも少し年上に見える男性で、上はTシャツ、下はスウェットパンツにサンダル、という非常にラフな格好をしていた。 男性がタバコをくわえた。 その瞬間、目が合った。 「この店、めっちゃええよ。絶対におすすめ」 と男性が力強く言った。 「はぁ……」 「そうなんですか?」 とおれたちがこたえた直後、男性は弾かれたように立ちあがった。なぜかその場でくるりと1回、ターン。さらに右手の指を思いきり「パー」の形に開き、こちらへ突きだしてきた。 「俺が言うんやから間違いない。びびっときたんよ。店の前を通りかかったときに、これや! と感じたっていうか。俺のこういう直感は当たる。こないだも不動産屋で家を決めてきてんけど、そんときもいっしょや。ぴんときた不動産屋に入って、希望を言って、そしたら自分でも考えもせんかったような好条件の物件が出てきて、もちろんすぐに決まり」 男性は一気にまくしたてた。 おれと岩崎さんは顔を見合わせた。一瞬、「変な人につかまっちまったぞ」とは思った。だが話をさえぎるのは難しそうだ。 「ここまではええな?」 なにがいいのかよくわからなかったが、とりあえずおれたちはうなずいてみせた。 「たとえばや。君たち、趣味はあるか? これだけはだれにも譲れない、ゆうような趣味。君はどうよ?」 びし! と岩崎さんの鼻面を指さす。 岩崎さんは眉根を寄せ、「そこまでの趣味、と言われると……すぐには思いつかないですね。お兄さんはなんかあるんですか? 趣味」と逆に訊きかえした。 男性は鋭い目つきになり、堂々と言った。 「伊吹マヤ」 「い……伊吹マヤ!?」 おれたちは思わず叫んでいた。 この人は天才だ、とおれは思った。 「伊吹マヤって、あの伊吹マヤですか? エヴァンゲリオンの? あれって趣味なんですか!? 1つのジャンルなんですか!?」 「違う、ジャンルとかそうゆうんとは違う! つまり……だれしも消滅してもかまわないと思える物事や概念、ゆうもんはあるやろう。たとえば俺やったら……俺はゴルフはやらへん。だから、バーディという言葉に興味はない。この言葉がこの世界から消滅しても結構。なんならゴルフという存在そのものが消えてもうてもかまわん。消滅ゆうんは、本当の意味での消滅やで? 最初からそれ自体が存在しなかったことになる、ゆうことやで? ほんで、そういう消滅しても許容できる存在に順位をつける、ゆうことをやってみたらええ。まずはこれを消滅させる、次に消滅させていいんはこれ、その次に消滅してがまんできるのはこれ、ゆう具合に。そうやってどんどん物事や概念を消滅させていったときに、最後に残るんはなにか、ゆう話よ。最も大切な物事あるいは概念」 「それが、お兄さんにとっては――」 「伊吹マヤ」 「ということですね」 己の価値観をここまで明確に定義できる、というのはすごいことだ。才能を感じる。むしろ才能しか感じない。 「そう。すべての物事や概念の先に、彼女はこう居座っているわけよ」 彼はギャングのボスが革張りの椅子に腰かけるようなポーズをしてみせた。エアで。 おれは同じポーズを真似てみた。 「なるほど。お兄さんの中では伊吹マヤがこう、どーんと居座っていると」 「ち……違うっ。マヤちゃんはそんなふうに座ったりせん!」 急に声が裏返った。 おれは、あわてて言いつのった。 「すいませんっ! いまのはあくまで存在としての重み、ということです。比喩表現です。もちろん彼女はこんなポーズなんかしません!」 「そう……そういうことよ」 彼は一瞬でも取り乱したことを恥じるように目を伏せた。 また目を上げ、今度はまた自信ありげに言った。 「うちの会社の連中も、君らぐらい物分りがよかったらええんやけどな。いまの話を理解させるのに、3年かかったわ」 「3年も!」 「大切なのは鍛えること自体とちゃうんよ。なんのために鍛えるのか、ゆうこと」 彼は演舞っぽい動きであらゆる方向に拳を繰りだし、今度は何回かまわった。 話の流れがまったく見えなかったが、もはやどうだってよかった。この偉大かつミステリアスな人物の深遠なる思考を、凡人のおれなどが洞察できるわけがない。 「その目的。俺が自分を鍛える最大の目的は、俺がいちばん格好ええと思うキャラのポーズを決めることやから」 「キャラの、ポーズを決める……?」 「そう――」 男性はまた何度か宙を殴り、流れるように動き、最後は半身になって「びし!」とおれのほうに右手の人さし指を突きつけてみせた。 「こう! こういうこと!」 そのポーズは、江頭2:50の決めポーズにしか見えなかった。 だからそう伝えた。 彼は頭をかきむしった。 「違う! なんで最も格好いいポーズがお笑いなんよ。鍛える究極の目標がそこなんよ!?」 「でも、江頭もかなり鍛えてると思いますけど――」 「だとしても、俺にとっての究極ではない! でも君にとって最も格好いい存在は江頭なのかもしれへん。いまの君は江頭へ至る過程なんかもしれへん。だから俺は江頭を、江頭を否定しない!!!」 彼は絶叫した。 ありがとうございます、と言うべきなのかどうか迷った。 言わなかった。 と、店のガラス扉が開き、メイドさんが心配そうな様子で顔を出した。 「あの、大丈夫ですか……?」 男性はくるりと向きなおり、親指でおれと岩崎さんを示した。 「この2人、新しいお客さん。俺がスカウトしたから」 「そうなんですか? ほんとに?」 メイドさんが問いかけてくる。 さすがに「違います」とは言えなかった。もはや入るしかない。 ある意味、根性と勇気と意気地のないおれたちをこの男性は後押ししてくれたわけで、この点については感謝しなくちゃいけないかもな、と思った。 その後に受けたマッサージは、それはもうこの上なく心地よく楽しいものであった。 |
| ←エッセイ目次 |