 | |
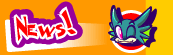 | |
 | |
 | |
| ●著者インタビュー ●イベントレポート ●リーダーズサーカス ●エッセイ ●TRPGリプレイ | |
 | |
|
| ←エッセイ目次 |
| 日々つれづれ 10年08月 テーマ 「 かさ 」 |
| 【10年08月30日 力造】 |
オレは焼いたレバーが 「苦手」 だ。 牛、豚、鳥は言うに及ばず、もし、それ以外の生き物のレバー料理を食うことになった場合、かなりイヤな顔をするだろう。 「そのレバーを焼いて食うなんてとんでもない!」 でも……食べられないほどではない。 さて、今回のテーマは 「かさ」 だ。 テーマが 「かさ」 なのに、なぜ好き嫌いの話をするかというと、「かさ」 から、過去の出来事を思い出したからだ。 その出来事にまつわるものとは……ずばり、 「しいたけ」 。 あの、デケエ 「かさ」 を持つ、きのこ界の真剣師。 そして、その裏側には狂気をもたらす無限のひだひだを隠し持つ――三千きのこ世界に終末を呼ぶ、黙示録の騎士である。 人には、1つや2つくらいダメな食べ物があるはずだ。 そして、オレの先輩には 「しいたけ」 がこれでもかというほどムリな人がいる。 「苦手」 ではない…… 「ムリ」 なのだ。 それは、先輩がオレの実家に泊まりにきた時のことだ。 とある夏休み――オレと先輩、そして複数の友人たちは休みを利用して、夜遅くまでオレの実家でTRPGを遊んでいた。 そして、次の日の朝。オレたちは気絶状態から復帰し、何事もなくリビングへと出ていった。 すると、オレの母が食事を用意してくれていた。夏の定番、そうめんである。 夜遅くまで騒いでいたというのに、ありがたいことだ。 オレたちは感謝しながら食卓につき、そうめんをいただくことにした。 ガラスの器に盛られた白い絹糸の如きたちは、その身を氷のなかで引き締めている。器のなかには細く切られたきゅうり、たまご、ハム、シロップ漬けのみかんとさくらんぼうなどが盛り付けられていた。 ……どうでもいいが、なぜ、そうめんの中にはみかんやさくらんぼうが入っているのだろう。 酢豚に入ったパイナップル。あれはわかる。 酢豚は絶妙な甘酸っぱさこそが命。ゆえに、その甘酸っぱさを出すために、あの南国育ちの憎いヤツが入っているという理由を理解している。 だが、そうめんにみかんやさくらんぼうを入れる理由はなぜだ? 別にそうめんは甘酸っぱくする必要はないだろう。 それに、みかんやさくらんぼうをメンツユにつけて食べる風習や掟は、我が日本には無い……はず。 あれか、濃いメンツユで口の中が辛くなった時、口直しをするためか? それともあれか? 涼か? 「ガラスに盛られた白く美しいそうめん……だが、それだけでは花がない。やはり白を際立たせるために、黄色や赤をそえなければ」 とか、そういうことなのか!? そして、そうめんと冷やし中華には、なぜさくらんぼうが乗ってるの!? 結局、色合いの関係なのだろうが、現在と変わらず無知で無教養な当時のオレは、食卓につきながらそんな病的かつアナーキーな妄想を展開していた。 そして、オレたちは貴重な糧を得たことに手を合わせ、ガラスの中に存在する麗しい絹糸たちを、昨夜演技した野盗と変わらぬ冒険者のように蹂躙し、口のなかへと運んでいった……その時である。 「――げおるぐッ☆」 先輩が、奇声と共にそうめんとツユを食卓に噴出した。 実に、よい悲鳴であった。 時が止まったかのようだった。 催眠術や超スピードではない。なにを言っているかわからないかも知れないが、本当のことなのである。 それを見た我々は、思わず驚愕した。「いったい何が起こったのか」 と。 そして、その答えは……メンツユの中にあった。 ……メンツユの中に、水で戻した 「しいたけ」 が刻んで入っていたのだ。 そして、我々は先輩の弱点が 「しいたけ」 であることを知っていた。 「なぜ、そんなものが入っているだ? もはや、テロではないか」 と考えたオレは、もっとも犯人と思しき人物に問いかけた。 「母上……」 「なんぞ?」 「なぜ、メンツユの中に刻んだしいたけが入っているのでござるか?」 「……炭水化物ばっかだと、ほらアレじゃん」 どれだ。 「母上、実は先輩氏は、しいたけがダメなのでござる」 「知らん」 ですよね。 「母上……しかし」 「喰えよ」 「……は?」 「他人の家で出された食い物を吐き出すなど、もってのほかじゃ。いいから喰えよ」 「しかし、先輩氏はしいたけが……」 「そんなもん、極限状態なら喰える。なら、ここを戦場だと思って……喰え!!」 今でも、あの恐怖と絶望の表情を忘れることができない。 こうして、先輩は泣いて侘びを入れることになった。 一時間ほどのやり取りがあったが結局、全ての片づけを先輩がするということで、喰うこと自体は許してもらえた。 オレはその日以来、夏を迎え、刻まれたしいたけを見るたびに思い出すのだ。 「苦手なものは、水で流し込めば喰えるが……しょせん、ムリなものはどれだけがんばっても、己の肉体が全力で拒否する」 のだと。 皆さんも、できるのなら 「ムリ」 な食べ物を、せめて 「苦手」 レベルまで克服しておくことをお勧めする。 さもないと……いつ、なにがきっかけで、ムリに喰わされるか、わからないからだ。 願わくば、そのような状況がこないことを、心からお祈する。 |
| 【10年08月23日 田中公侍】 |
| 「チューブじゃなくて、缶のほうがオススメ」 手が荒れる。 夏も冬もだ。夏は暑すぎれば指の間に水泡ができ、冬はアカギレがひどい。 今年の夏は猛暑ゆえ、もうすでに何度か水泡が破けている。 なにせ痒い。仕事でキーボードなど叩いている場合ではない。 薬などを塗って対処するが、まだ有効な市販品を見つけていない。 間違ってムヒなぞ塗ってしまったときは、あまりの痛さに手足を凍らせてしまいたくなった。 ……聞いてて気持ちのイイ話ではない気がしてきたぞ。いいのか? そもそも、どうやら砂アレルギーという奴らしい。 砂に含まれる塩分や鉄分がまずいらしいのだ。 まったく気にしたことはなく、自覚したのは成人してからだった。 幼稚園児の頃、毎日砂場で遊んで来ては、謎の痒みや痛みと戦っていた。 主に掻いて。ダメダメだね。 夏も冬も拳を握ると血が滲み出し、白い靴下は家に帰ると赤茶色になっている。 自分の所有物などは構わなかったが、さすがにバイトを始めた頃に 「これは見た目にまずい」 となった。 いろいろ試した結果、寝ている間に「NI○EA」のハンドクリームに綿の手袋と靴下をしておく、というのが良かった。 それまでの痛みも消え、しばらくの間症状がまったく出なくなる。すばらしい。 が、しかし。出費がかさむ。 ハンドクリームを両足にも塗るものだから、消費量が半端ない。さらに、手袋と靴下も一夏、一冬で4〜5回替える。 手足が潤った代わりに、財布が 「カサカサ」 になったという話。 今回は苦しいな……。 |
| 【10年08月18日 龍口明眞】 |
本人の意志により削除しました。 |
| 【10年08月12日 大井雄紀】 |
友人のメッセンジャーのコメント。 「ラベルは衣服、キャップは眼鏡に脳内変換してペットボトルの分別をする」 天才かと思いました。 お久しぶりです。大井雄紀です。 さて、今回のエッセイのテーマは 『かさ』 だそうです。 というわけで、先日の出来事をつらつらと書き綴っていきます。 先日、僕は14時ごろSNE近くのJR三ノ宮駅に降り立ちました。 この日は夕方からセッションがあるだけで、17時に出社すればよかったので3時間ほど余裕があります。 僕は本屋やゲームショップを渡り歩くため、あえて早く到着するよう計画を立てていました。 朝早くに準備を済ませ、サイコロとルールブックを鞄に詰め込んでいます。 もちろん、本やゲームを買ったとき用に、鞄にスペースを空けておくことも忘れていません。 僕 「ふっ、計画通り……」 完璧に思えた計画ですが、一点だけミスがありました。 三ノ宮駅から見上げた空は灰色で、ときおり僕の頬に水滴が触れます。 この日は、雨だったのです。 僕 「なん、だと……」 僕は戦慄します。 この日の僕は、傘を持っていなかったのです。 銃を持たず戦場へときてしまった新兵のような心境です。 僕 「現地調達しかないか……」 歴戦の戦士のごとくさっそうと駅を駆け、僕はコンビニへと突入。 武器(傘)を手に取ったところで、525円という本が一冊買える値段に驚愕します。 ですが、武器を持たないことには戦いは始まりません。 コンビニ店員さんの 「この人傘持ってこなかったんだ……プッ」 という生暖かい目(被害妄想)に見送られ、僕はコンビニを出ました。 ――バッ。 雨の降る空に向かい、買ったばかりの傘を広げます。 「あなたのことを守るわ」 そんな傘の声が聞こえてきた気がします。 すると、僕の脳内では傘が瞬時に美少女へと変貌します。 僕 「ふっ。よろしくな、カトリーヌ」 名前をつけたことで、僕と傘はもはや長年連れ添ったカップルの気分。 僕とカトリーヌは戦場という名の本屋へ旅立ちました。 一時間後の15時30分。 激戦を終えた僕はコーヒーショップへと入ろうとします。 出社までにはまだ時間があったので、コーヒーを飲みつつ戦利品を確認しようとしたのです。 店に入る前に、店先にあったビニールでカトリーヌを包みます。雨の日の本屋さんなどでよく見かける、濡れた傘を包むあれです。 僕 「カトリーヌ、おめかししようか」 カトリーヌ 「これ、透けてて恥ずかしいわ」 僕 「はっはっは、それがいいんじゃないか」 と脳内でまったくどうでもいい妄想しつつ入店。 三十分ほど本を読み、僕はSNEに向かうため席を立ちました。 僕 「カトリーヌ。僕を導いてくれ」 ――バッ。 カトリーヌは返事代わりに、地面に向かってビニールを広げます。 ふと、そのとき気づいてしまいました。 雨が……止んでいる。 周りを見渡してみれば、誰も傘をさしていません。 天を見上げてみれば、灰色の雲よりも青色のほうが多くの面積を占めています。 間抜けなぐらいの青空は、世界の広さを伝えてくれます。 まるで自分がちっぽけな存在なことを教えてくれるようです。 僕の口が、自然と歌を紡ぎだします。 僕 「さわやか三組〜♪」 あれ、なんでだろう。 さわやかな午後だというのに、視界が滲むよママン……。 手に持つカトリーヌの質感が、やけに冷たく感じます。 ――カチ。 僕は、カトリーヌを閉じました。 涙をこらえて、僕は歩き出します。 その後、僕は会社へ行く途中に立ち寄ったコンビニで、カトリーヌと別れました。 悲しいことですが、所詮一時の女だったのです。 あんなに愛していたのに、気持ちが冷めてしまったのです。 ……ぶっちゃけ、入り口の傘さしに忘れてきてしまいました。 僕 「ごめん、カトリーヌ」 会社に到着し、カトリーヌがいないことに気づいた僕はそう呟きました。 もう、なんど同じこと(コンビニに傘を忘れてくること)を繰り返したのかわかりません。 僕 「こんな悲しいこと、二度と起こっちゃいけない! 財布の中身的な意味で!」 カトリーヌ(『傘』)との別れを経て、僕は『重ねて』そう思うのでした。 |
| ←エッセイ目次 |